どうも!モリオ(@yome__kawaii)です。
大学入試とは切っても切れないセンター試験ですが、2019年度(2020年1月実施)が最後になります。
2020年度からは、センター試験に代わり「大学入学共通テスト」が実施されます。試験形式が変わる節目ですね。
とは言っても、2021年の試験を受験するのは(浪人しなければ)今の高校2年生からなので、現時点で受験生の方は現行の「大学入試センター試験」の対策をしなければいけません。
センター試験は、毎年1月中旬の土・日曜の2日間に全国で一斉に実施されます。受験者数は例年50万人以上の日本最大規模の試験です。
国公立大学の一般入試受験者は、原則としてセンター試験を受験しなければいけません。
また、多くの私立大学でもセンター試験の成績が利用できる「センター試験利用方式」を設定しています。センター試験の対策は私立の一般入試よりもやりやすいので、利用しない手はありませんね。
大学進学を考える受験生にとってはセンター試験対策は必須といっても過言ではないでしょう。
とは言っても、センター試験の重要性や勉強の開始時期は学校で教えてくれないことがほとんどなので、今日はセンター試験対策について書いていきます。
センター試験の勉強はいつから始めればいいの?

国公立大学を志望する場合には、センター試験と各大学の二次試験の両方の勉強をする必要があります。
いずれも基礎学力が必要ですが、各試験に対応した対策をしなければなりません。
3年生の8月頃までに基礎的な学力を身に付けてから9月以降にセンター試験(英語のリスニングを除く)と二次試験対策を同時に進めて行くと良いでしょう。
マーク式の問題は正答に至るまでの論理を自分で考えなくても良いという特徴があります。
これに対して二次試験(特に数学)は自分で解き方の道筋を考えなければならないため、勉強方法が全然違います。
春の時期からセンター試験対策を始めてしまうとマーク式の問題に特化してしまい、二次試験で求められる論理的な思考をするための対策がおろそかになってしまいます。
そのため、センター試験の過去問や練習問題に取り組むのは秋以降がベストです。ただし英語のリスニングだけは、なるべく早く始めるようにしましょう。
もちろん、私立大学をセンター試験を使って受験しようとしている方や、国立大学の志望大学のセンター比率が高い大学を受験する場合は、
高校3年生になった時点からセンター試験対策のみを重点的に行って言っても問題はありません。
センター試験勉強法の基本方針

勉強方法の基本方針ですが、二次試験と重なる科目とセンター試験のみの科目に分けて考えることができます。
センター試験のみの科目(理系であれば国語や社会など)はマーク式の問題に特化して勉強を進めましょう。
センター試験と二次試験の両方を受験する科目であれば、二次試験対策を中心にして演習を進めるようにすると良いでしょう。
記述式の問題を中心に演習を進めれば、マーク式の問題対策にもなるからです。
二次試験と重ならない科目については、マーク式の問題を解くためのテクニックを身に付けることで短時間で効率的に勉強をするようにしましょう。
センター試験対策に多くの時間を割きすぎて、二次試験対策のための時間が奪われてしまわないように注意が必要です。
両者のバランスが大切です。
二次試験の方が難易度が高いからといってそちらの対策ばかりしていると、センター試験の点数が悪くて足切りや諦めなければいけないこともあります。
大学ごとにセンター試験と二次試験の得点の比率は出ているので参考にしてバランスを取るようにしましょう。
センター試験で高得点を獲得するための勉強法の肝

センター試験は基本的な問題が多く出題されるという特徴があるので、教科書レベルの基本事項をしっかりと押さえておく必要があります。
教科書から万遍なく出題されるので、不得意分野を放置しない事が大切です。
問題数が多いので、じっくり考える思考力よりも手際の良さを必要とします。
センター試験やマーク模試の過去問集を入手して、何度も解いてトレーニングを積むと良いでしょう。
センター試験の本番は短い試験日程で多くの科目の試験が実施されるので、午後は疲労との戦いになります。
普段は解けるような易しい問題でも、本番では疲労のせいでミスをしてしまうことがあります。
試験当日は1日に多くの科目を受験することを意識し、朝から夕方まで集中力を持続させられるようにする事が大切です。
そのためには本番と同じ時間・科目の組み合わせで過去問を何度も解いて、しっかりと体力をつけておくようにしましょう。
センター試験の対策は過去問がメインです。意識して過去問演習を実施しましょう。
センター試験の得点戦略
センター試験の特徴は問題数が多いので時間との闘いになります。
難易度に関係なく、各問題の配点がほぼ一定であるという特徴もあります。
限られた時間で得点を稼ぐためには難易度が高い問題を見分けて、時間がかかりそうな設問を後回しにしましょう。
特に数学は最後の方の設問の難易度が高くて時間を取られてしまうので、見切りをつけるための判断力が必要です。
英語のリスニングが苦手な受験生も多いですが、子音を聞き分けることがポイントです。
そのためには、音楽を聴く時よりも音量を高めに設定しておきましょう。
センター試験は問題に“クセ”があり、テクニックを身に付けてしまえば少ない労力で解ける場合があります。
テクニックを身に付けるためには、直近数年分の過去問や予備校のマーク模試の問題を何度も解いて慣れることが大切です。
ちなみに予備校で実施されるマーク模試は的中率が高く、本番で似たような問題が出題されるケースがあります。
まとめ

センター試験は基本的な問題が中心ですが、大学によっては二次試験よりも配点が高く設定されているケースがあります。
二次試験で出題されない科目の実力を試す目的で、センター試験を活用する国公立大学が増えています。
特に最近は理系学部でも日本語の読解力を重視する傾向があり、現代文の配点が高めに設定されている大学があります。
国公立大学を志望する受験生は二次試験対策に多くの時間を割きたいと思うかもしれません。
それでもセンター試験と二次試験の合計点で合否が決まるので、きちんと対策をしておく必要があります。
二次試験では合格圏内であっても、センター試験の結果が不振で志望校の変更をしなければならなくなる受験生も少なくありません
センター試験を受験すると科目が増えてしまいますが、効率良く学習を進めるようにしましょう。







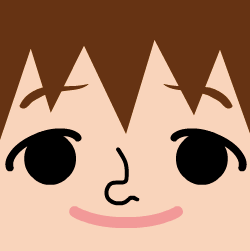





























今年、長年付き合っていた恋人と結婚しました。
うちのかわいい鬼嫁について記事を書いていきます。
少しでも、読んでくださった方の役に立てればこの上ない幸せです。