どうも!モリオ(@yome__kawaii)です。
初詣にいくと「厄年の早見表」って必ずありますよね。
特にいつも気にしていませんが…、嫁が来年「本厄」の年でした。
ということは今年は「前厄」になるわけですが…。
厄年ってなんなんかわからなくないですか??


どこの家庭でもそんなもんですかね?
前厄って何をしなくちゃいけないのか、厄年とは何?について書いていきます。
最近ついてないな…、と思ったら厄年かもしれない?!

「最近ついてないな…」「最近良いことないなー」、などと感じたことはありませんか?
厄年(やくどし)は、日本などで厄災が多く降りかかるとされる年齢のことである。科学的な根拠は不確かで、陰陽道由来とされるものの出典は曖昧である。しかし、平安時代にはすでに存在し、根強く信じられている風習である。
遥か昔から日本にあった厄という言葉…。
科学的には証明されていないものの平安時代から厄年なるものがあります。
ちなみに厄年でない人も厄払いに行っても問題ありません。
厄年ではなくてもなんとなくついていない…、身の回りで嫌なことが続くという方は、安心して一年を過ごす祈願として厄払いしてもいいかもしれませんね。

厄年とは何?まずは厄年の年齢は?

厄年は数え年で判断します。
数え年は1月1日で満年齢に2歳を加え、その年の誕生日から満年齢に1歳を加えます。
男性が大厄の年は女性は小厄。女性が大厄の年は男性は小厄となります。
つまり、嫁の年齢が今年の1月1日に30歳なので+2歳して数え年は32歳ということです。
そもそもなんで厄年があるかというと、昔の人は自分に降りかかる災難は「厄病神」などの仕業と考えていましたので、その災難を防ぐために厄払いなどが始まったようです。

そして「厄年」というのは特に災難が多く降りかかるとされている年齢のことです。
段階を踏んで、「前厄」「本厄」「後厄」と3年間厄年となります。
「厄年」は人生の転換期とされています。運気が下がり肉体的にも精神的にも調子を崩しやすいと昔から考えられています。

男性42歳、女性33歳が「大厄」と呼ばれていて数回おとずれる本厄の中でも、最も注意が必要な年齢とされています。

数え年で男性42歳(40歳の年)、女性33歳(31歳の年)が「大厄」と呼ばれていて、体や環境の変化で一番災難が起こりやすいと言われている年のことです。
語呂合わせでも42(死に)、33(散々)など良いことがなさそうなイメージですね。
厄除けと厄払いの違いは?
お正月のTVCMとかで…、「厄除けは…大社。」「厄払いは…。」とか厄除けと厄払いという言葉がでてきますが違いはご存知ですか?
厄年に神社やお寺で厄を払ってもらうのが厄年の風習ですが場所によって正式には「厄除け」「厄払い」に分かれます。
- 厄払い(厄祓い)
『祓う』という字を使っているように、厄払いとは神社に出向いて祈願祈祷してもらうものの事を言います。厄払いは自身に災厄をもたらすモノを自身の身から祓ってもらう為に祈願祈祷してもらうものとなっています。 - 厄除け
厄除けは災厄などの邪気が寄り付かないように祈願祈祷してもらうものとなっています。災厄が自身に近寄らないようにする予防・保険の意味合いが強いです
結局はどちらも「災難を寄せ付けない」ためにすることです。
「厄除け」「厄払い」では祈祷きとうの儀式内容に違いがあります。
親戚などに贈り物をする・出産をする・よく身につけているものを落とすなどの行為は厄落としになると言われています。
厄除け・厄払いのタイミングは?

厄除け・厄払いに行く時期に関しては、年始から節分までに済ませるのが良いとされています。
もちろん地域によって違いもあります。
そして節分を過ぎても別に問題がありません。「思い立ったら吉日」なので六曜を特に意識しなくても大丈夫とされています。
厄除け・厄払いにルールや服装は?
多くの方は普段着で行くことが多いようです。
ですが、格式の高い神社などではあまりにもラフすぎる格好だと受け付けてもらえない場合もあるようなので…、せっかく行ったのにNGになるよりはなるべく軽装や露出の多い服装は避けてフォーマルな服装で行くほうがいいですね。
- 男性
紺や黒などの落ち着いた色のジャケットスタイル - 女性
スーツもしくは落ち着いた色の無地ワンピース
神社やお寺によっては礼服を指定しているところもあります。
神社などのHPや問い合わせした時に事前にチェックをしていきましょう。
厄除け・厄払いの金額の相場は?

気になる金額についても見ていきましょう。
大きな神社では事前に金額が明示されているところがあります。
祈祷料・御布施は気持ちなので、金額に関しては特に明示のない神社やお寺であれば自分の財布と相談して決めましょう。
心配であれば、事前に問い合わせをして祈祷料を確認しても失礼には当たりません。
なるべく新札が良いとされています。
袋の指定は特にないですが、「白い封筒」か「紅白の蝶結びの熨斗袋」が一般的です。
上段に、縦書きで
- 神社の場合は「初穂料」
- お寺の場合は「御布施」
下段に厄除け・厄払いを受ける人の名前を書きます。
ちなみに祈祷料・御布施は神社やお寺の受付のときに渡します。
まとめ

厄年はネガティブなイメージが先行しますが…、「厄」ではなく《役》として捉える風習もあるらしいです。
大役を担う・役目を与えられる年と捉えれば厄払いは成功を祈願してお参りに行こうというポジティブなイメージに変わりますね!
そして、本来は「前厄」「本厄」「後厄」「お礼参り」と4回くらい行くみたいです。


嫁は厄とか関係ない大雑把な性格なので…助かりますが。
災難が起こる前に神頼みしてきたいと思います。







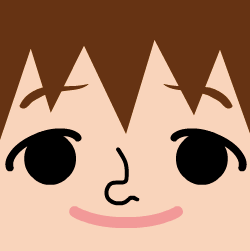



























今年、長年付き合っていた恋人と結婚しました。
うちのかわいい鬼嫁について記事を書いていきます。
少しでも、読んでくださった方の役に立てればこの上ない幸せです。